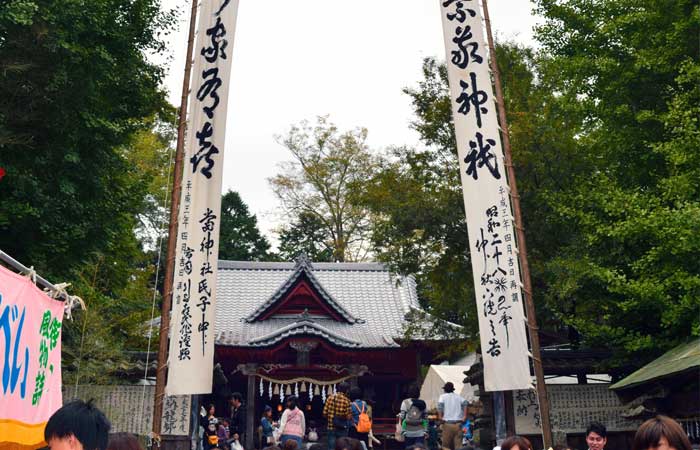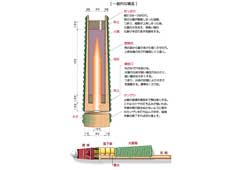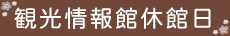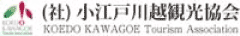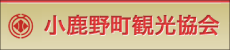龍勢まつり
龍勢まつりとは
龍勢の製法
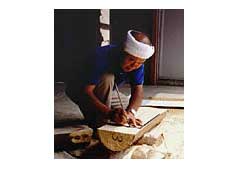 |
祭りの日が近づくと、それぞれの耕地や奉納者団体では、矢柄となる青竹をさがし、根本から切り、先端の枝葉を残して道ばたに立てます。 |
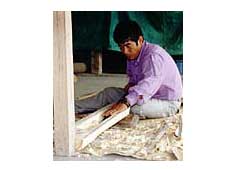 |
墨入れにそって松材をくり抜きます。 |
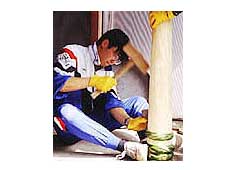 |
くり抜いた松材を2つ合わせ、竹のタガをかけていきます。 |
 |
硝石、炭、硫黄を混ぜ黒色火薬を調合します。 |
 |
火薬筒に黒色火薬を詰めていきます。 |
 |
筒の底に錐で穴をもみ、噴射口を作ります。 |
 |
祭りの前日、龍勢に取り付けられるショイモノ(背負い物)を作ります。 |
 |
前日に仕上がり、きれいに化粧された龍勢です。 |
打ち上げ
 |
打ち上げの順番がくると、自分たちの龍勢を櫓までかついでいきます。 |
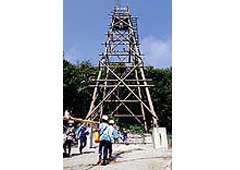 |
高さ約20メートルの打ち上げやぐらに龍勢をセットします。 |
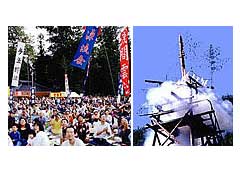 |
点火の一瞬を数万人の観客が息をのみ待ちます。 |
 |
昇りつめた龍勢は、落下を始めるやいなや仕掛けを披露します。 |
 |
しかし、いつも成功するとはかぎりません。 |
基本情報
| 名称 | 龍勢まつり |
|---|---|
| 場所 | 秩父市吉田 椋神社周辺 |
| 開催日 | 10月第2日曜日 |
| 駐車場 | あり |